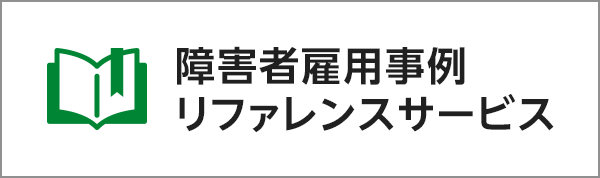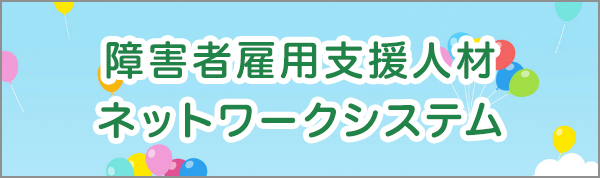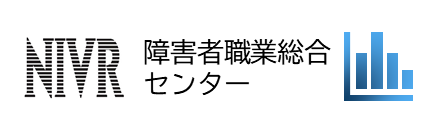Q&A 障害者の方からよくある質問
在宅就業とは
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q1 在宅ではどんな働き方がありますか。 |
A1 在宅で働く場合には、企業に雇用され在宅で勤務する(ここでは「在宅勤務」といいます)場合と雇用関係がなく請負契約で働く(ここでは「在宅就業」といいます)場合があります。在宅勤務では、週20時間以上(週4~5日勤務)働いて、障害者雇用率の算定対象となっているケースが多いようです。 在宅就業では、在宅勤務よりも短い時間で働いているケースが多いようです。また、受注があった時だけ働くケースもあります。 |
| Q2 在宅就業支援団体とはなんですか? |
A2 在宅就業支援団体(厚生労働大臣に申請、登録を受けている団体)は、障害者の在宅就業を支援するため、発注元の事業主と在宅就業障害者との間に立って、障害者に対しては仕事の発注や各種相談支援等を行い、事業主に対しては納期、品質に対する保障を担う役割をはたしています。 |
| Q3 在宅勤務や在宅就業について相談できる機関はありますか? |
A3 在宅就業支援団体では、在宅で働くことを希望する障害者の相談や訓練を行っています。また、厚生労働大臣の登録は受けていないものの、相談や訓練を行っている団体もあります(障害者の在宅就業を支援する団体)。当ホームページに掲載の近隣または興味のある活動をしている団体にお問合せされると良いでしょう。 |
| Q4 在宅ではどんな仕事がありますか? |
A4 当ホームページ資料集には実際に在宅で仕事をされている方の就業事例を掲載しております(在宅事例集の送付も行っております)。掲載されている事例では次のような業務を行なっており、パソコンやITを活用した業務が多くなっています。
|
スキルアップ
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q1 在宅就業支援団体ではどのような訓練をしていますか? |
A1 在宅就業支援団体で実施されている主な技能訓練には次のようなものがあります。訓練の受講方法として、通所やe-ラーニング、週に1回程度、講師が家庭訪問し個別指導をする方法があります。 ※なお、訓練内容や受講方法は在宅就業支援団体ごとに異なりますので詳細は各団体にお問い合わせください。 訓練内容
また、技能訓練に加え次のようなビジネスマナーやコミュニケーションの講習も行なっているところがあります。
|
| Q2 居住している県に在宅就業支援団体がありません。他に相談や訓練をしているところはありますか? |
A2 在宅就業支援団体以外にも、障害者の在宅就業を支援する団体があります(Q&Aよくあるご質問「在宅就業とは」A3で紹介)。 e-ラーニングについては、当ホームページのe-ラーニング機関を参照してください。また、厚生労働省の「障害者の態様に応じた多様な委託訓練」(別ウィンドウで開きます)では通所が困難な重度障害者の方などが、在宅でIT技能などを習得する「e-ラーニングコース」を実施しています。 障害者ITサポートセンターではパソコンを活用するうえでの相談、パソコンボランティアの派遣などを行っています。 |
在宅就業を行う上でのポイント
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q1 体調管理で気をつけることはありますか? |
A1 自宅で在宅就業を行なう場合、上司や同僚が体調の変化に気づきにくいことがあります。休憩を入れず作業に熱中するあまり疲労の蓄積や、作業姿勢、残存機能の酷使によって、痛みや機能低下、障害悪化などを引き起こす場合があります。 特にVDT作業※1については、入出力デバイス・周辺機器がストレスなく利用できる状態かどうかだけでなく、座位の取り方なども大きなポイントになります。自身がよく知っている地域の作業療法士や理学療法士など専門家に相談するのがよいでしょう。通院やリハビリの時間などが必要な場合は、会社と労働日・労働時間を協議した上で、契約にきちんと盛り込んでおく事が望ましいでしょう。 体調不良を我慢した結果、長期の欠勤につながるなどのことのないよう、自分の健康状態を適切に会社に伝えることが重要です。 ※1 ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力、文章、画像などの作成、プログラミングなどを行う作業 |
| Q2 会社とコミュニケーションをとる時に気をつけることはありますか? |
A2 わからないことは放置せず、早めに連絡を取ることが必要です。メールではニュアンスが伝わらないこともあるので、必要に応じて電話や定期的な出勤、上司に自宅に訪問してもらうなどして打ち合わせすることも大切です。 また、在宅勤務の場合は、会社で勤務する場合よりも職場の人間からの声かけが少なくなるため、他者とのコミュニケーションが一層重要となります。 |
アンケートのお願い
皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。
※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。